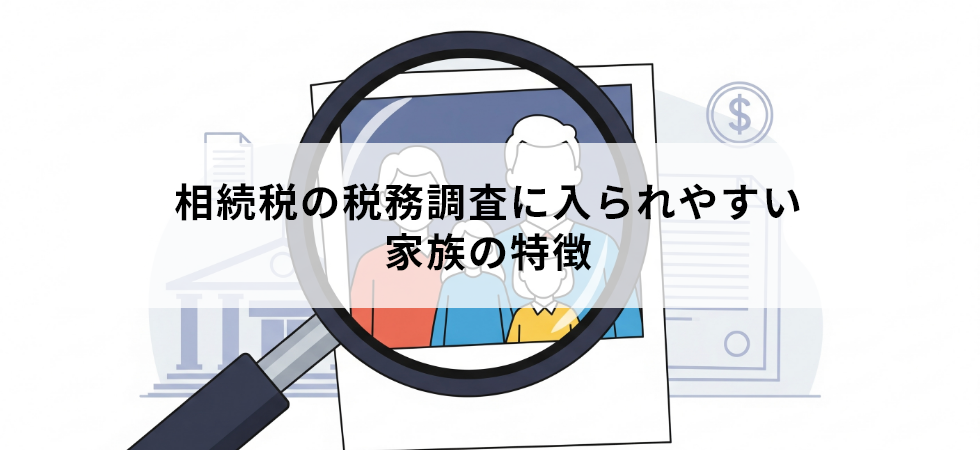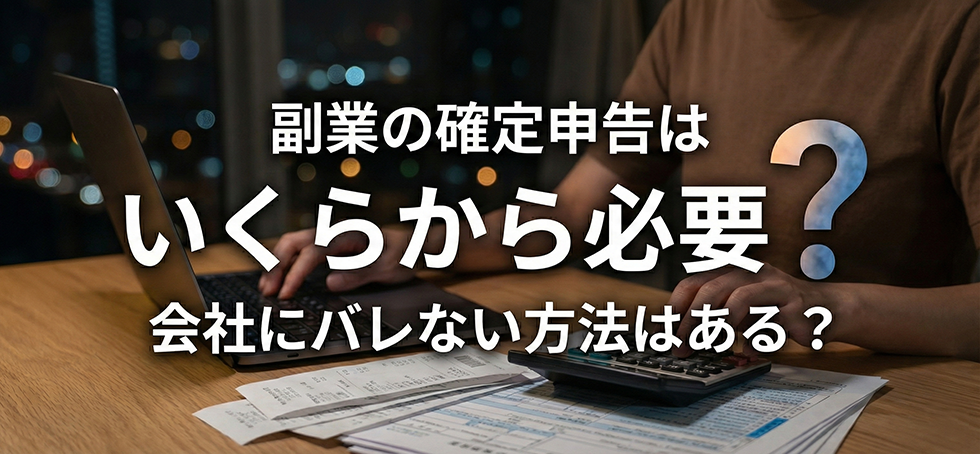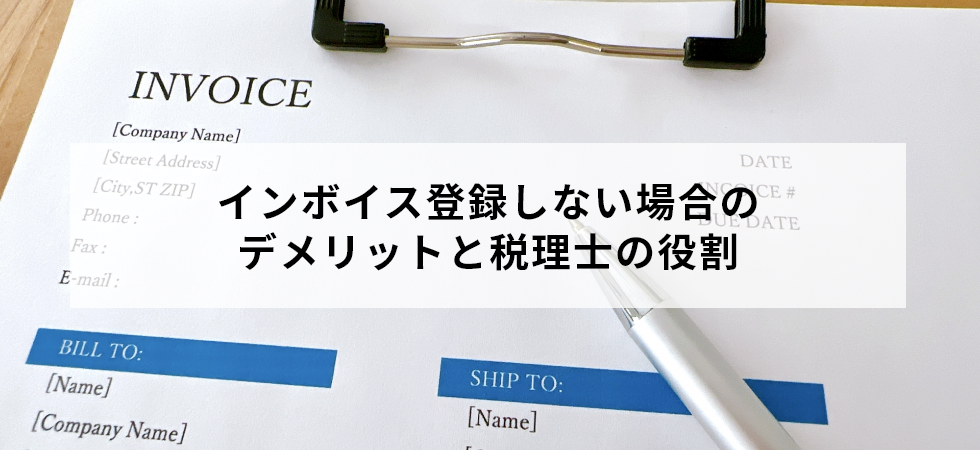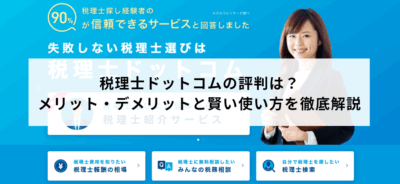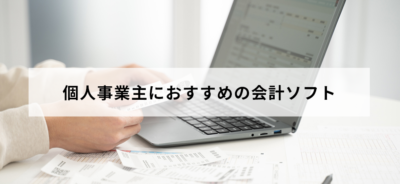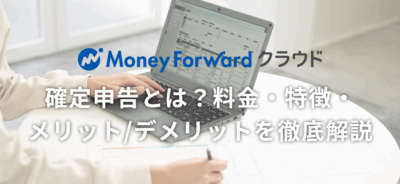個人事業主の消費税、いつから払う?納税義務の判定と計算方法
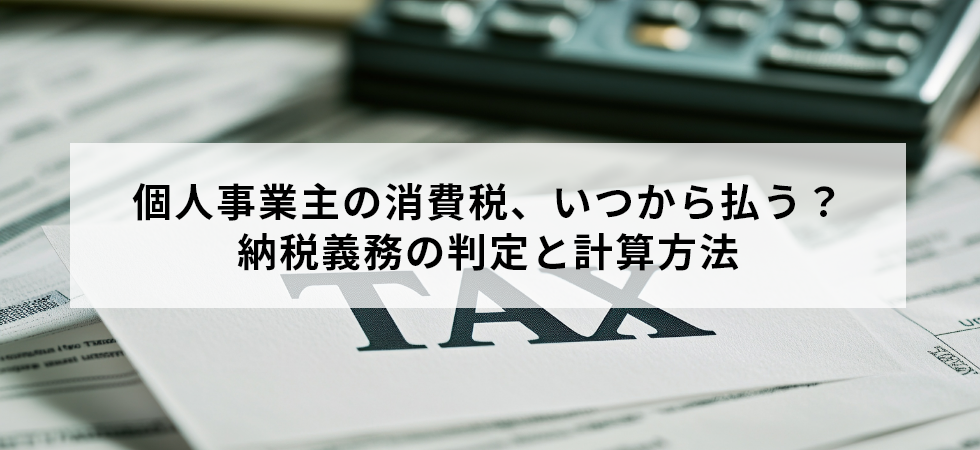
個人事業主として事業を続けていると、やがて「売上1000万円」という大きな節目が見えてきます。これは、事業が順調に成長している証であると同時に、多くの事業主が「消費税」という新たな税金と向き合うことになる、重要な転換点です。
「売上が1000万円を超えたら、すぐに消費税を払うの?」「一体どうやって計算するんだろう?」「何か準備しておくことはある?」
こんにちは。「税理士コラボネット」の小林です。この「1000万円の壁」は、多くの個人事業主が税理士への相談を本格的に考え始める、最も多いきっかけの一つです。消費税の仕組みは非常に複雑で、知らないままでいると、将来の資金繰りに大きな影響を与えかねません。
この記事では、売上1000万円が近づいてきたあなたのために、消費税の納税義務が「いつから」発生するのか、その判定方法と具体的な計算方法、そして今からやっておくべき準備について、プロの視点から分かりやすく解説します。
目次
結論消費税の納税義務は「2年前の売上」で決まる
まず、最も重要なルールからお伝えします。個人事業主の場合、消費税を納める義務があるかどうか(課税事業者になるかどうか)は、原則として「2年前の売上」で判定されます。
この「2年前」の年のことを「基準期間」と呼びます。例えば、2023年の売上が1000万円を超えた場合、あなたが消費税の納税義務を負うのは、2年後の2025年の申告から、ということになります。すぐに納税が始まるわけではないので、慌てずに準備する時間があります。
あなたはどっち?納税義務を判定する2つの期間
納税義務の判定には、この「基準期間」に加えて、もう一つ「特定期間」という例外的なルールがあります。ご自身の状況がどちらに当てはまるか、確認してみましょう。
1.基準期間(2年前の課税売上)
これが基本のルールです。2年前の1月1日から12月31日までの課税売上高が1000万円を超えている場合、その年(当課税期間)は課税事業者となります。
2.特定期間(前年の上半期の課税売上)
これは例外ルールです。もし、2年前(基準期間)の売上が1000万円以下であっても、前年(特定期間)の1月1日から6月30日までの半年間の課税売上高が1000万円を超えた場合、その年から課税事業者となります。(※売上高の代わりに、給与支払額で判定することも可能です)このルールは見落としがちなので、事業が急拡大している方は特に注意が必要です。
消費税の計算方法は2種類!「原則課税」と「簡易課税」

晴れて課税事業者になった場合、納める消費税額の計算方法には、大きく分けて2つの種類があります。どちらを選ぶかで、納税額が大きく変わる可能性があるので、しっかり理解しましょう。
- 原則課税
計算式:『お客様から預かった消費税』-『仕入などで支払った消費税』
これが基本の計算方法です。売上で預かった消費税から、経費や仕入で支払った消費税を差し引いて、差額を納めます。正確な計算のためには、全ての経費について、消費税額をきちんと記録しておく必要があります。 - 簡易課税制度
計算式:『お客様から預かった消費税』-(『お客様から預かった消費税』×『みなし仕入率』)
簡易課税制度は、仕入時に支払った消費税を個別に計算するのではなく、「預かった消費税のうち、一定の割合を支払ったものとみなして」計算する、中小企業のための簡便的な方法です。この「みなし仕入率」は、事業の種類によって40%~90%と定められています。
この制度を利用するには、基準期間の課税売上高が5000万円以下であることと、事前に届出を提出する必要があります。
プロの視点納税義務が発生したら、まずやるべきこと
課税事業者になることが決まったら、以下の3つのアクションをすぐに検討しましょう。
1.税理士に相談し、どちらの課税方式が有利か判断する
「原則課税」と「簡易課税」、どちらを選ぶかは非常に重要な経営判断です。例えば、大きな設備投資を予定している場合は、「原則課税」の方が支払う消費税が多くなるため、還付を受けられる可能性があります。あなたの事業内容や将来の計画によって、どちらが有利かは変わってきます。この判断は専門知識が必要なため、必ず税理士に相談しましょう。
2.消費税分の資金を別管理する
お客様から受け取った消費税は、あなたのお金ではありません。国に納めるまでの一時的な「預かり金」です。この感覚を身につけ、売上の一部を消費税納税用の口座に分けて管理するなど、納税資金を確実に確保する習慣をつけましょう。これを怠ると、納税時期に資金繰りが苦しくなる原因になります。
3.法人化(法人成り)を本格的に検討する
売上1000万円を超えたタイミングは、法人化を検討する(ベストなタイミングについてはこちら)絶好の機会でもあります。法人を設立すると、最大2年間、消費税の納税が免除されるという大きなメリットがあるからです。税金面だけでなく、社会的信用など他のメリットも多いため、税理士に相談してシミュレーションしてみることをお勧めします。
「個人事業主の消費税」まとめ
- 個人事業主の消費税の納税義務は、原則として2年前の売上高が1000万円を超えた場合に発生する。
- 前年の上半期だけで売上1000万円を超えた場合も、納税義務が発生する「特定期間」のルールに注意。
- 計算方法には「原則課税」と「簡易課税」の2種類があり、どちらが有利かは事業内容による。
- 納税義務が発生したら、①税理士に相談 ②納税資金の確保 ③法人化の検討をすぐに始めるべき。
消費税の納税義務が発生することは、あなたの事業が順調に成長している証です。これは新たなステージに進むためのステップと前向きに捉え、正しい知識を持って、計画的に準備を進めていきましょう。
当サイト「税理士コラボネット」では、消費税やインボイス制度に精通し、個人事業主の皆様のステージアップを力強くサポートしてくれる先生方をご紹介しています。
税理士探しのご相談もお受けしています
ご自身で選べない、どの先生に相談していいか分からないという方は、下記フォームよりお気軽にご相談ください。ご状況に合った最適な税理士探しをサポートさせていただきます。