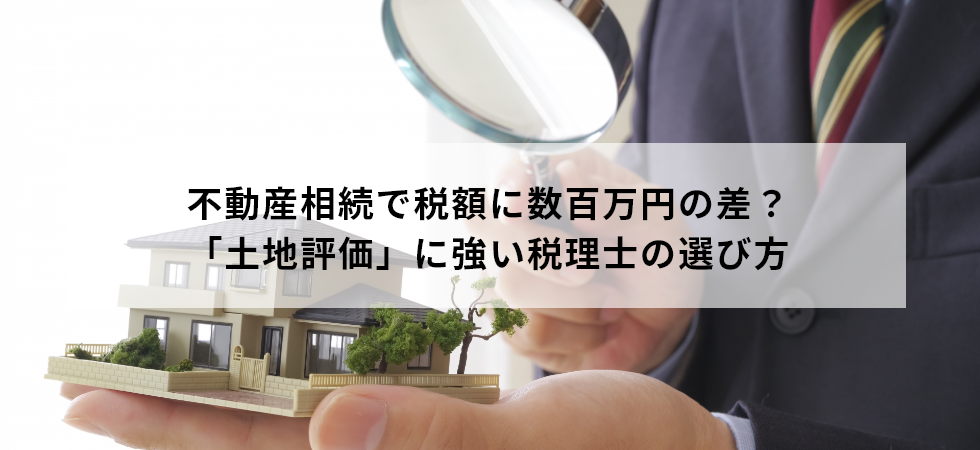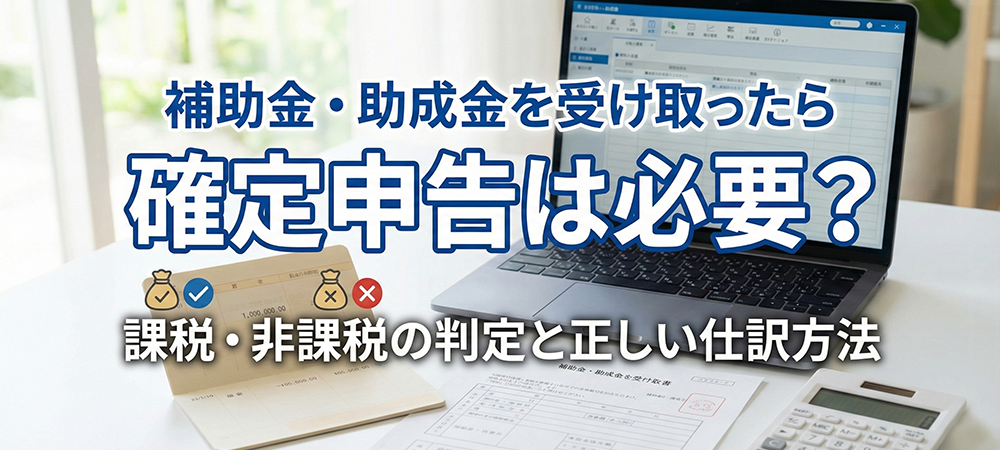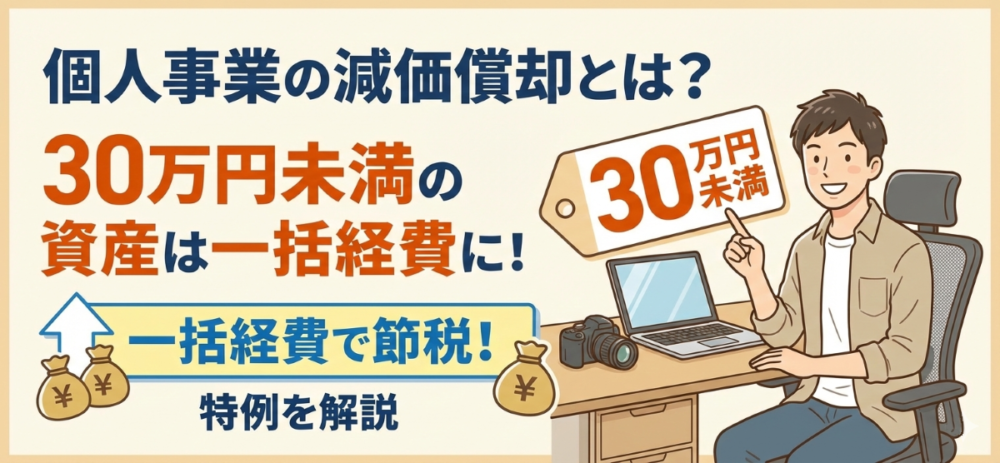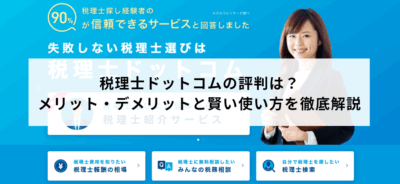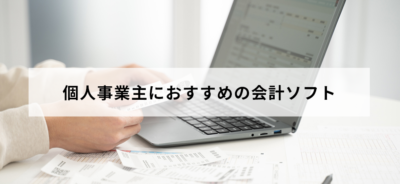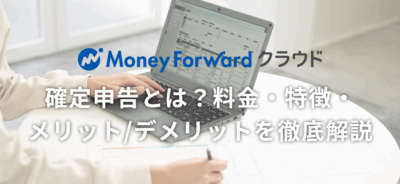相続税の税務調査に入られやすい家族の特徴とは?調査のリアルと税理士の役割
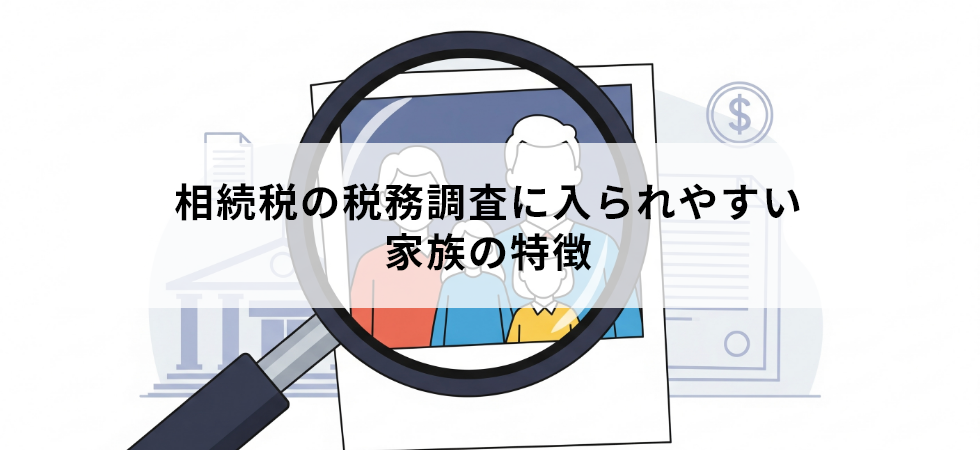
「うちは財産も少ないし、真面目に申告したから大丈夫」
相続税の申告を終えた後、多くの方がそう思っています。しかし、残念ながら、相続税は他の税金と比べて「税務調査」の対象となる確率が非常に高い税金の一つです。ある日突然、税務署から「相続税の件で…」と電話がかかってくる可能性は、決してゼロではありません。
こんにちは。「税理士コラボネット」の小林です。私は全国の税理士の先生方から、数多くの相続税調査のリアルな実情を伺ってきました。そこから見えてきたのは、「調査対象に選ばれやすい家族」には、いくつかの共通した特徴があるという事実です。
この記事では、いたずらに不安を煽るのではなく、正しい知識で備えていただくために、税務調査の対象となりやすい家族の具体的な特徴と、その調査のリアル、そして万が一の際にあなたと家族を守る「税理士の役割」について、プロの視点から詳しく解説します。
目次
相続税の税務調査、その実態とは?
まず、相続税の税務調査がどれくらいの割合で行われているかご存知でしょうか。国税庁の発表によると、年度によって多少の変動はありますが、申告された案件のうち、およそ10件に1件、つまり約10%が調査の対象になっていると言われています。これは他の税金に比べて非常に高い割合です。
調査官は、KSKシステム(国税総合管理システム)というデータベースを使い、亡くなった方(被相続人)とその家族の過去の所得や資産状況を、我々が想像する以上に詳細に把握しています。その上で、「申告された財産額が、把握している情報と比べて少ないのではないか」という観点で調査対象を選定しているのです。
税務調査に入られやすい家族5つの特徴

全国の税理士の先生方から伺った「調査対象に選ばれやすいケース」には、以下のような特徴があります。ご自身の状況と照らし合わせてみてください。
1.申告された財産額が「少ない」家族
これは意外に思われるかもしれませんが、最も多いパターンです。税務署が事前に把握している被相続人の所得や資産状況から予測される財産額よりも、申告された額が明らかに少ない場合、「財産隠しや申告漏れがあるのではないか」と第一に疑われます。特に、預貯金の申告額が少ないケースは要注意です。
2.「名義預金」や「タンス預金」が疑われる家族
被相続人が、配偶者や子供、孫の名義で預金口座を作っていた「名義預金」は、税務上は被相続人の財産と見なされます。これらが申告から漏れているケースは非常に多く、税務署も重点的にチェックしています。また、生前に多額の現金を引き出しているにもかかわらず、手元現金の申告(タンス預金)が少ない場合も、「どこかに隠しているのでは?」と疑われる原因になります。
3.「海外資産」や「暗号資産(仮想通貨)」を保有していた家族
近年、特に調査が強化されているのが、海外の不動産や預金、そしてビットコインなどの暗号資産です。これらの資産は、国内の資産に比べて税務署が把握しにくいため、申告漏れが起きやすいと見なされています。保有している場合は、細心の注意を払って申告する必要があります。
4.過去に「贈与」の事実があったが、申告されていない家族
生前に、被相続人から子供や孫へまとまった金額の贈与があったにもかかわらず、贈与税の申告が行われていない場合も、調査の対象となりやすいです。特に、亡くなる前数年以内(現在は7年以内)の贈与は、相続財産に加算して計算する必要があるため、厳しくチェックされます。
5.「税理士の署名がない」申告書を提出した家族
申告書をご自身で作成して提出することも可能ですが、「税理士の署名がない」ということは、「税のプロによるチェックを経ていない」ということを意味します。税務署から見れば、計算ミスや解釈の間違いが起きやすいと判断されるため、調査対象となる確率は格段に上がると言われています。
調査のリアル当日、調査官は何をどこまで見るのか?

では、実際に調査官が来た場合、どのようなことが行われるのでしょうか。
調査は通常1~2日間、自宅で行われます。調査官は、事前に通知した資料(通帳や証券会社の取引記録など)を確認するだけでなく、家の中を回り、書斎の机の中や金庫、仏壇などを確認することもあります。これは、タンス預金や、申告されていない貴金属、美術品などがないかを確認するためです。
また、相続人に対して、被相続人の生前の暮らしぶりや趣味、交友関係などについて、世間話のような形で質問を重ねます。これは、申告されていない財産の手がかりを探るための、調査官の常套手段です。
プロの視点税理士は、あなたと家族を守る「防波堤」
こうした厳しい調査において、税理士はあなたと家族を守る「防波堤」として、3つの重要な役割を果たします。
- 調査前の「防衛準備」
相続税に強い税理士は、調査官がどこに疑問を持ち、何を聞いてくるかを熟知しています。事前にシミュレーションを行い、「この質問にはこう答えましょう」「この資料は不要なので出さないようにしましょう」といった具体的な防衛策を準備してくれます。 - 調査当日の「盾」となる
調査当日は、税理士が必ず立ち会います。調査官からの不適切な質問や、誘導的な発言に対しては、専門家として毅然と制止します。あなたが直接答える必要はなく、「税理士に確認します」と一言伝えれば、税理士が法的な観点から的確に応答してくれます。 - 調査後の「交渉役」
もし何らかの申告漏れを指摘された場合でも、すぐに修正申告に応じる必要はありません。税理士は、その指摘が法的に妥当なものか、解釈の余地はないかを検討し、税務署との交渉を行います。この交渉力によって、最終的な納税額が変わることも少なくありません。
「相続税の税務調査」まとめ
- 相続税の税務調査は約10件に1件の高い確率で行われる。
- 申告財産が少ない、名義預金が疑われる、海外資産があるといった家族は調査対象になりやすい。
- 税理士の署名がない申告書は、調査対象となる確率を上げてしまう。
- 調査では、書類だけでなく自宅の中の確認や、家族へのヒアリングも行われる。
- 税理士は、調査前の準備、当日の立会い、事後の交渉という3つの場面であなたと家族を守る。
税務調査は、精神的に大きな負担を伴います。しかし、その負担は、信頼できる税理士に依頼することで大幅に軽減できます。そして何より、相続税に強い税理士が作成した質の高い申告書は、そもそも調査対象になりにくいという最大のメリットがあります。
当サイト「税理士コラボネット」では、相続税申告はもちろん、その後の税務調査対応にも豊富な経験を持つ、信頼できる先生方をご紹介しています。万が一の事態に備え、安心してご家族の財産を守りたい方は、ぜひ一度ご相談ください。
税理士探しのご相談もお受けしています
ご自身で選べない、どの先生に相談していいか分からないという方は、下記フォームよりお気軽にご相談ください。ご状況に合った最適な税理士探しをサポートさせていただきます。