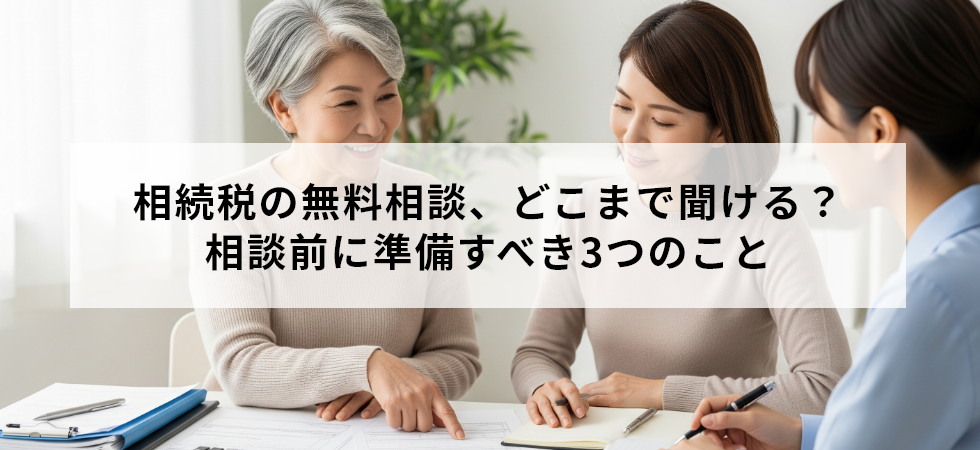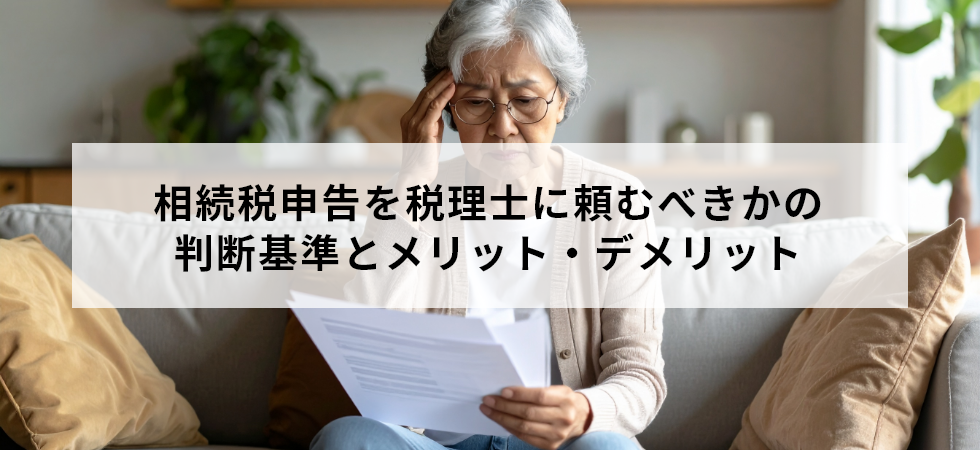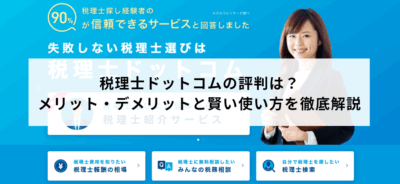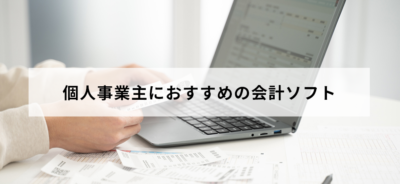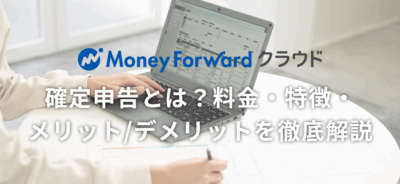相続税申告の報酬、誰が払う?相続人間で費用を公平に分担する方法
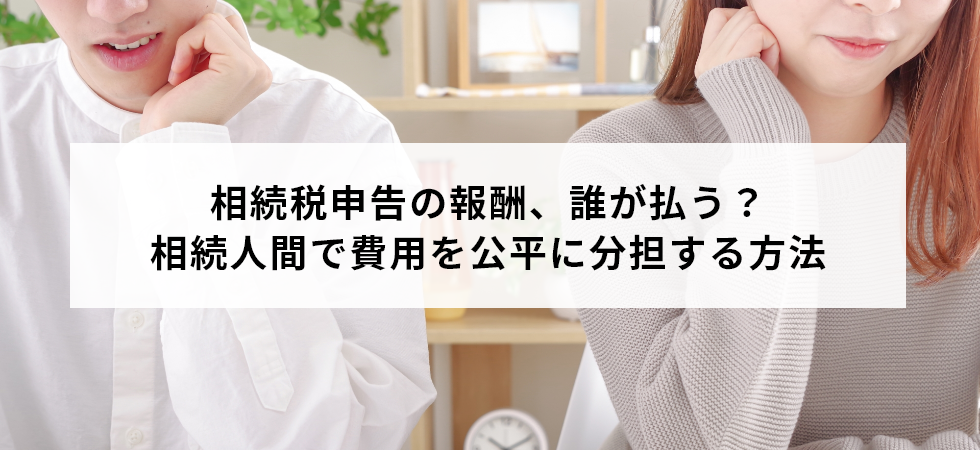
相続税の申告を税理士に依頼しようと決めたとき、遺産分割そのものとは別に、もう一つ家族間で話し合っておくべき重要なお金の問題があります。それは、「税理士に支払う報酬は、誰が、どのように負担するのか?」ということです。
「代表で手続きを進める長男が全部払うべき?」「いや、財産を多くもらう人が多く払うのが筋だろう」「そもそも、その費用は経費として遺産から引けないの?」
この費用負担のルールを曖昧にしたまま進めてしまうと、後々、相続人間で思わぬトラブルの火種になりかねません。
こんにちは。「税理士コラボネット」の小林です。私は全国の税理士の先生方から、相続税申告が無事に終わった後、この費用負担の問題で家族の間にしこりが残ってしまった、という残念なケースを伺うことがあります。
この記事では、あなたが円満な相続を実現するために、相続税申告の税理士報酬を誰が払うべきか、その法律上の考え方と、トラブルを避けるための公平な分担方法について、プロの視点から詳しく解説します。
目次
結論:法律上の決まりはなく、「相続人全員で負担する」のが一般的

まず結論から申し上げます。税理士報酬を「誰が払わなければならない」という法律上の明確な決まりはありません。
ただし、税理士への依頼は、特定の誰か一人のためではなく、相続人全員が正しく申告・納税を完了させるために行うものです。そのため、実務上は「相続人全員で、何らかの基準に基づいて公平に分担する」のが最も一般的で、トラブルの少ない方法と言えます。
また、よくある誤解として「税理士報酬は、経費として遺産総額から差し引ける」というものがありますが、これは間違いです。税理士報酬は、相続税の計算上、経費(債務)として控除することはできません。
最も公平な分担方法は?3つのパターンを比較
では、具体的にどのように分担すれば、全員が納得しやすいのでしょうか。一般的に用いられる3つの方法をご紹介します。
1.各相続人が取得した財産の割合で「按分」する
これが最も合理的で、広く採用されている方法です。例えば、遺産総額が1億円で、長男が6,000万円(60%)、長女が4,000万円(40%)を相続し、税理士報酬が100万円だった場合、長男が60万円、長女が40万円を負担します。財産を多く受け取る人が、その分多くの費用を負担するため、公平感が高いと言えます。
2.相続人が均等に「頭割り」で負担する
相続人が2人なら50万円ずつ、3人なら約33万円ずつ、というように、単純に相続人の数で均等に割る方法です。計算がシンプルで分かりやすいのがメリットですが、財産の取得割合に大きな差がある場合、「少ししか相続していないのに、なぜ同じ額を…」と不満が出る可能性があります。
3.代表の相続人が一旦立て替え、遺産から精算する
手続きを主導する代表の相続人(例えば長男)が、一旦個人の財産から税理士報酬を支払い、遺産分割が完了した後、その金額を遺産の中から精算(回収)する方法です。支払いがスムーズに進むメリットがありますが、事前に全員の合意を得ておかないと、「勝手に払った」と後から揉める原因にもなり得ます。
プロの視点:トラブルを未然に防ぐ、たった一つの重要なこと
どの分担方法を選ぶにせよ、将来のトラブルを確実に防ぐために、たった一つだけ、絶対にやっておくべきことがあります。
それは、「遺産分割協議の場で、税理士報酬の負担方法についてもしっかりと話し合い、その内容を遺産分割協議書に明記しておく」ということです。
「税理士報酬〇〇円については、各相続人が相続財産の取得割合に応じて負担するものとする」
このように一文を加えておくだけで、後から「言った」「言わない」の水掛け論になるのを防ぎ、全員が納得の上で手続きを進めることができます。
税理士に相談する際には、「費用負担についても、遺産分割協議書に盛り込みたい」と伝えれば、適切な文案を作成してくれるはずです。
「相続税申告の報酬分担」まとめ
- 相続税申告の税理士報酬を誰が払うかという法律上の決まりはない。
- 税理士報酬は相続税の計算上、経費として差し引くことはできない。
- 最も公平で一般的なのは、各相続人が取得した財産の割合に応じて負担する「按分」方式。
- どんな分担方法を選ぶにせよ、必ず遺産分割協議書にその負担方法を明記することが、トラブル防止の鍵。
相続税申告の費用負担は、金額の大小に関わらず、家族間の感情をこじらせかねないデリケートな問題です。手続きを始める前に、ぜひご家族でこの記事を参考に話し合い、円満な解決方法を見つけてください。
当サイト「税理士コラボネット」では、申告手続きだけでなく、こうした相続人間の円滑なコミュニケーションまでサポートしてくれる、経験豊富な先生方をご紹介しています。
税理士探しのご相談もお受けしています
ご自身で選べない、どの先生に相談していいか分からないという方は、下記フォームよりお気軽にご相談ください。ご状況に合った最適な税理士探しをサポートさせていただきます。