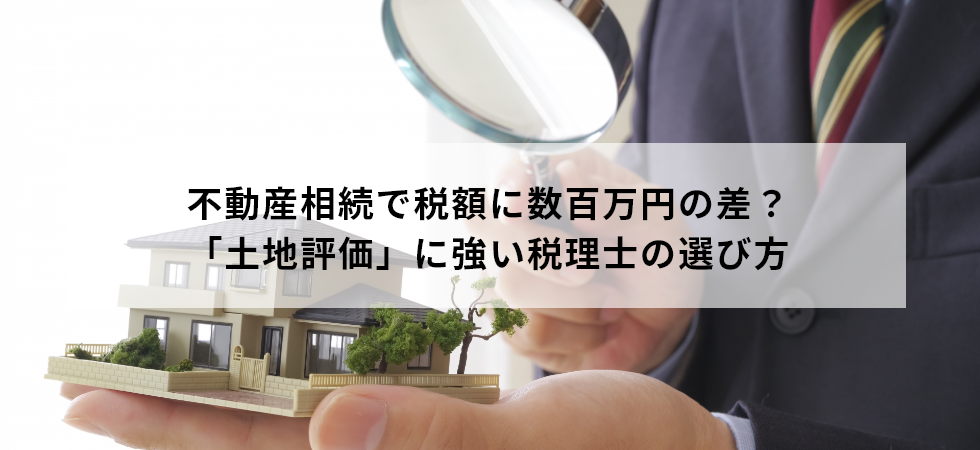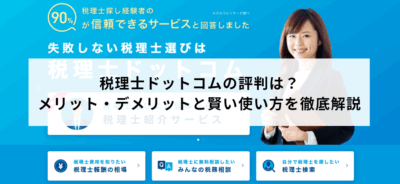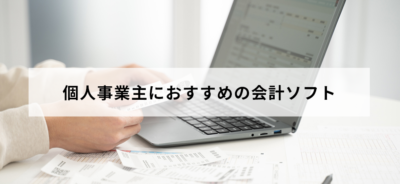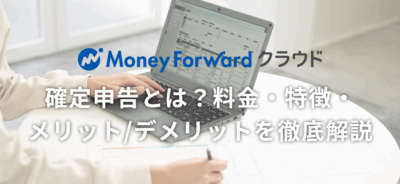生前贈与は税理士に相談すべき?メリット・費用と「やってはいけない」贈与
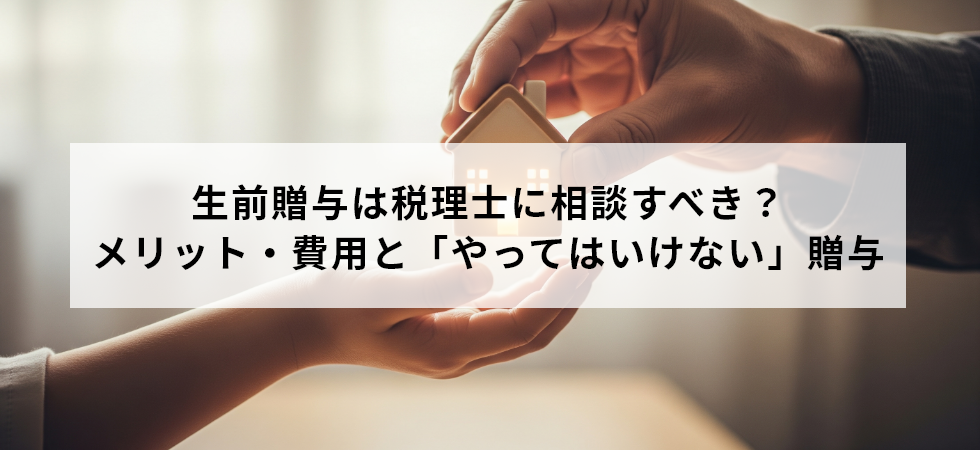
「将来、子供たちに少しでも多くの財産を残してあげたい」「元気なうちに、自分の意思で財産を分け与えたい」
将来の相続を考えたとき、多くの方が「生前贈与」という選択肢を思い浮かべるのではないでしょうか。生前贈与は、相続税対策として非常に有効な手段ですが、その一方で、やり方を間違えると、かえって多額の税金がかかるなどの大きなリスクも潜んでいます。
こんにちは。「税理士コラボネット」の小林です。私は全国の税理士の先生方から、「良かれと思ってやった生前贈与が、後々大きなトラブルになってしまった」という悲しいケースを数多く伺ってきました。
この記事では、将来の相続対策を真剣に考えているあなたのために、「生前贈与を税理士に相談するメリット」から、絶対にやってはいけない「名ばかり贈与」のリスク、そして税理士に依頼した場合の費用まで、プロの視点から詳しく解説します。
目次
そもそも「生前贈与」とは?相続との違い
生前贈与とは、その名の通り「生きているうちに、自分の財産を誰かに無償で与える」ことです。これに対し、「相続」は亡くなった後に財産が引き継がれることを指します。
生前贈与には「贈与税」が、相続には「相続税」がかかりますが、この二つの税金は税率の構造が異なります。この税率の違いを利用し、計画的に生前贈与を行うことで、将来の相続税の負担を軽減するのが、相続税対策としての生前贈与の基本的な考え方です。
生前贈与を税理士に相談する3つの大きなメリット
では、なぜ生前贈与を自分だけで判断せず、税理士に相談すべきなのでしょうか。その理由は、単に税金の計算が複雑だから、というだけではありません。
1.最も効果的な「非課税枠」の活用法を提案してくれる
生前贈与には、年間110万円まで非課税となる「暦年贈与」や、2500万円までが非課税となる「相続時精算課税制度」など、様々な非課税制度があります。どちらの制度を使うのが有利かは、あなたの資産状況、年齢、家族構成によって全く異なります。税理士は、あなたの状況を総合的に判断し、最適な制度の組み合わせを提案してくれます。
2.納税額だけでなく「二次相続」まで見据えた計画を立ててくれる
例えば、相続税対策として、配偶者に多くの財産を贈与したとします。しかし、その配偶者が亡くなった際(二次相続)に、子供たちが多額の相続税を負担することになっては意味がありません。プロの税理士は、今回の贈与だけでなく、その先の二次相続まで見据え、家族全体で見て最も税負担が少なくなるような、長期的な視点でのアドバイスをしてくれます。
3.「やってはいけない贈与」のリスクから守ってくれる
これが最大のメリットかもしれません。良かれと思って行った贈与が、後から税務署に「これは贈与と認められません」と否認されてしまうケースがあります。そうなると、多額の追徴課税やペナルティが発生する可能性があります。税理士は、法的に正しく、誰からも文句のつけようがない「完璧な贈与」の実行をサポートし、あなたと家族を将来のリスクから守ってくれます。
要注意絶対にやってはいけない「名ばかり贈与」と、その末路
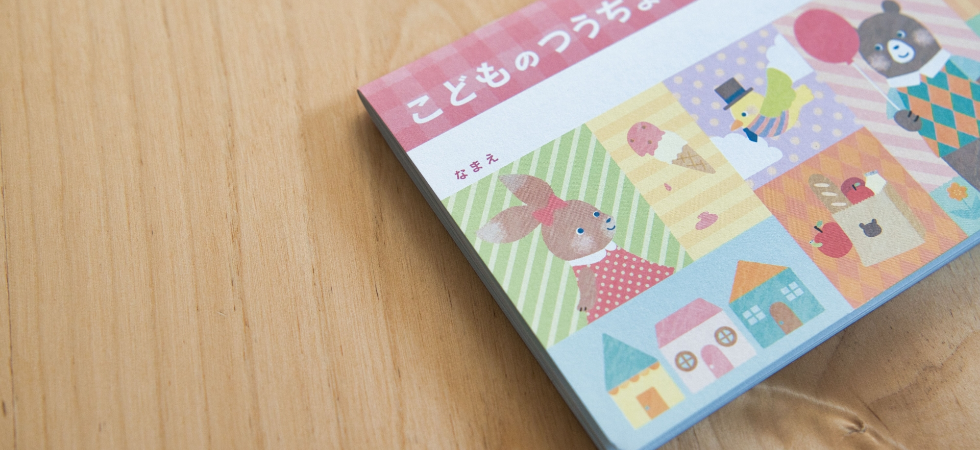
税務署に贈与を否認される代表例が、「名義預金」と見なされるケースです。これは、形式上は子供や孫の名義の口座にお金が移っているものの、実質的には親(贈与者)が管理していると判断される預金のことで、「名ばかり贈与」とも呼ばれます。
では、なぜ以下のような贈与が「名ばかり」と判断されてしまうのか、その理由を一つずつ見ていきましょう。
- 子供や孫に内緒で、勝手に口座を作って入金していた
【なぜダメなのか?】贈与は、お互いの「あげます」「もらいます」という意思の合致があって初めて成立する法律行為(契約)です。贈与された側がその事実を知らなければ、そもそも贈与は成立していない、と税務署は判断します。 - 通帳や印鑑を、贈与した親が管理し続けていた
【なぜダメなのか?】口座の名義が子供や孫になっていても、その通帳や印鑑を親が管理しているということは、いつでも親が自由にお金を引き出せる状態、ということです。つまり、その財産を実質的に支配しているのは親のままであり、名義を借りているだけ、と見なされてしまいます。 - 贈与された側が、そのお金を自由に使えない状態だった
【なぜダメなのか?】贈与とは、財産の所有権を完全に相手に移すことです。たとえ子供名義の口座にあっても、「私が死ぬまで使ってはダメだよ」などと、自由な使用を制限している場合、それはまだ子供自身の財産になったとは認められません。 - 贈与契約書を作成していない
【なぜダメなのか?】口約束だけの贈与も有効ですが、税務調査(についてはこちら)では「本当に贈与の事実があったのか」という客観的な証拠が求められます。贈与契約書がなければ、贈与の意思があったことを証明できず、「親が勝手に資金を移動させただけ」と判断されても仕方ありません。
このように、良かれと思ってやったつもりが、税法の観点からは全く贈与と認められないケースは山ほどあります。だからこそ、計画段階から税理士に相談し、法的に完璧な形で実行することが不可欠なのです。
税理士に依頼した場合の費用相場
では、実際に生前贈与の相談や手続きを税理士に依頼した場合、費用はどれくらいかかるのでしょうか。
- 相談料
1時間あたり5,000円~20,000円程度 - 贈与税の申告書作成
5万円~15万円程度(贈与する財産の価額や種類による) - 生前贈与コンサルティング(年間)
10万円~(長期的な贈与計画の立案、実行サポート、贈与契約書の作成などを含むパッケージ)
「生前贈与と税理士」まとめ
- 生前贈与は有効な相続税対策だが、やり方を間違えると大きなリスクを伴う。
- 税理士に相談するメリットは、最適な非課税枠の活用、二次相続対策、そして「やってはいけない贈与」からの防御。
- 子供や孫に内緒で口座を作るなどの「名ばかり贈与」は、税務署に否認され、重いペナルティの対象となる。
- 税理士への費用は、将来支払うはずだった高額な税金やリスクを回避するための「保険」と考えることができる。
大切な家族に、円満に、そして賢く財産を引き継ぐために、生前贈与は非常に有効な手段です。しかし、その実行には、税務の専門家である税理士のサポートが不可欠です。
当サイト「税理士コラボネット」では、生前贈与や相続対策の経験が豊富な、信頼できる先生方をご紹介しています。あなたの家族の未来を守るための第一歩として、ぜひお気軽にご相談ください。
税理士探しのご相談もお受けしています
ご自身で選べない、どの先生に相談していいか分からないという方は、下記フォームよりお気軽にご相談ください。ご状況に合った最適な税理士探しをサポートさせていただきます。