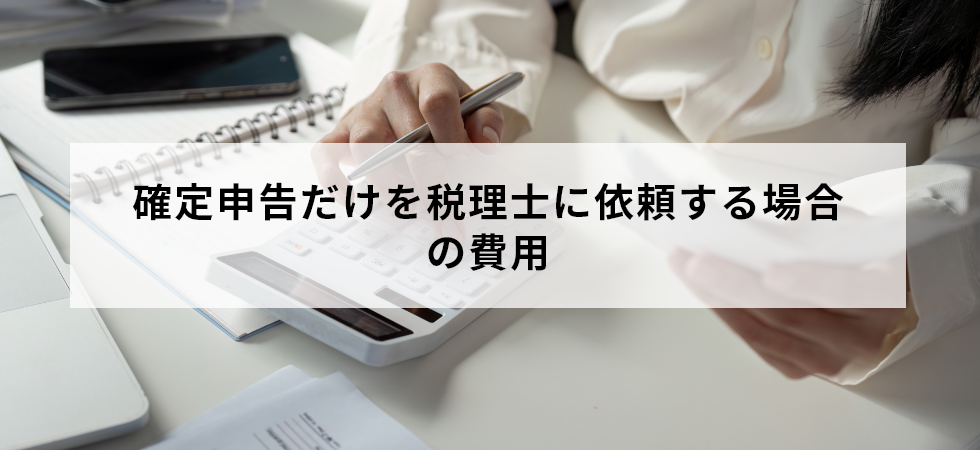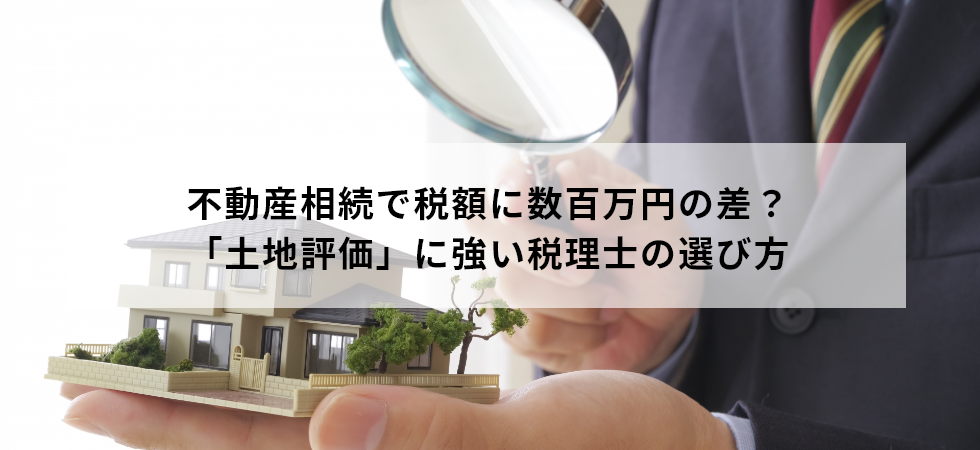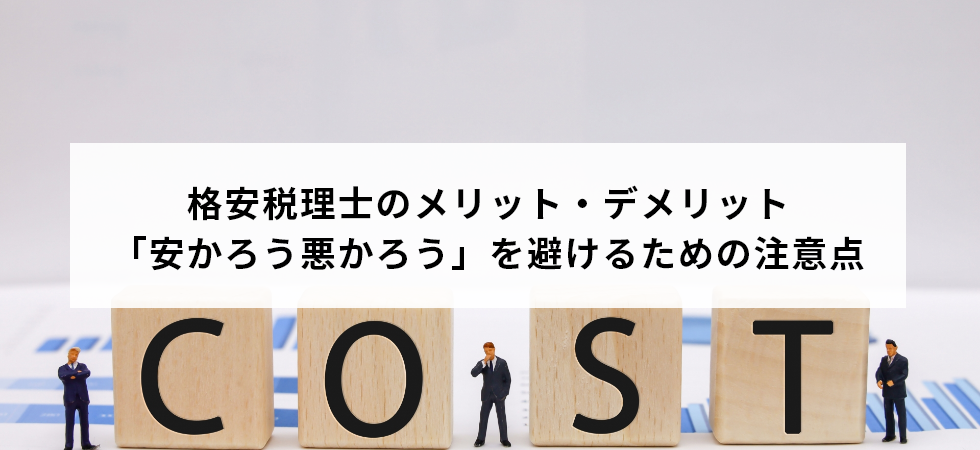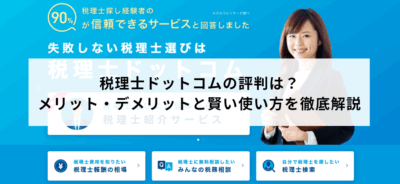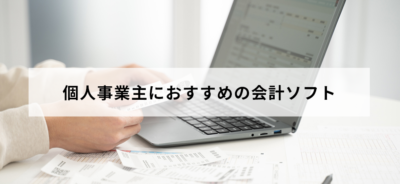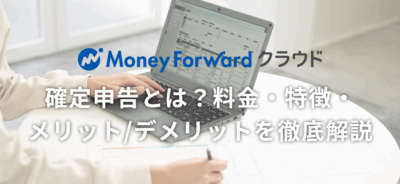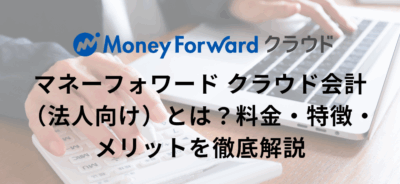顧問税理士とは?業務内容・費用相場から選び方までプロが徹底解説
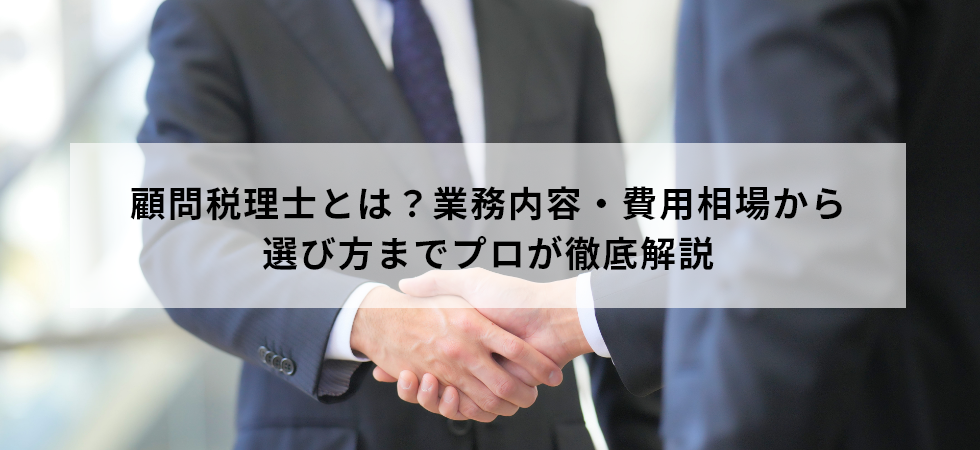
「税理士と顧問契約を結んで毎月顧問料を支払っているが、正直その価値があるのか分からない…」「これから会社を設立するが、そもそも顧問税理士は必要なのだろうか?」
こんにちは。「税理士コラボネット」の小林です。日々多くの経営者様から、顧問税理士に関するこのようなお悩みを伺います。顧問税理士は、会社の成長を力強く後押しする「経営パートナー」となり得る一方で、その役割や価値が分かりにくいために、関係が形骸化してしまっているケースも少なくありません。
そこでこの記事では、顧問税理士に関するあらゆる疑問を解消するため、「そもそも顧問税理士とは何か?」という基本から、具体的な業務内容、費用相場、そして失敗しない選び方・探し方まで、プロの視点で網羅的に解説します。この記事一本で、あなたの会社に最適な税務パートナーを見つけ、その価値を最大限に引き出すためのすべてが分かります。
目次
そもそも顧問税理士とは?スポット契約との根本的な違い
まず、「顧問税理士」が、年に一度の確定申告だけを依頼する「スポット契約」の税理士と何が違うのかを理解することが重要です。
スポット契約が、急な発熱時に病院へ行く「対症療法」だとすれば、顧問契約は、会社の健康状態を毎月チェックし、生活習慣のアドバイスを受けながら病気を予防し、さらにパフォーマンスを向上させるための「主治医」や「パーソナルトレーナー」のような存在です。
つまり、過去の数字を整理して申告するだけでなく、会社の日々の状況を継続的に把握し、未来の経営判断に必要なサポートをタイムリーに受けるためのパートナーシップ契約。それが顧問契約の本質と言えるでしょう。
顧問税理士はどこまでやってくれる?業務内容を一覧で解説

では、顧問契約を結ぶと、税理士は具体的にどこまでの業務を担ってくれるのでしょうか。契約内容は税理士事務所によって様々ですが、一般的に「顧問料に含まれることが多い業務」と「別途費用(オプション)となることが多い業務」に分けられます。契約前には必ず書面で業務範囲を確認しましょう。
顧問料に含まれることが多い業務
- 日常的な税務・会計相談
日々の取引で生じる「この経費は認められるか?」「この勘定科目は何か?」といった疑問に対し、電話やメール、チャットツールなどで迅速に回答します。経営判断に迷った際の、信頼できる相談相手となります。 - 月次試算表の作成と経営状況の報告
毎月の会計データを基に試算表を作成し、会社の財政状態や経営成績を報告します。これにより、経営者は自社の状況をリアルタイムで把握し、問題点の早期発見につなげることができます。 - 節税対策に関するアドバイス
決算間近になって慌てて対策するのではなく、年間を通して継続的な視点から効果的な節税策を提案します。未来の設備投資計画なども踏まえた、戦略的なアドバイスが期待できます。
別途費用となることが多い業務
- 記帳代行
領収書や請求書、通帳のコピーなどを預かり、会計ソフトへの入力作業を代行します。自社に経理担当者がいない場合に依頼することが多いですが、その分、顧問料は高くなります。 - 決算申告
年に一度の決算書および法人税・消費税・地方税の申告書を作成し、税務署へ提出します。これは税理士の独占業務であり、通常は月額顧問料の4~6ヶ月分が別途「決算料」として発生します。 - 給与計算・年末調整
役員や従業員の毎月の給与計算、賞与計算、そして年に一度の年末調整を行います。従業員数に応じて費用が設定されていることが一般的です。 - 税務調査対応
税務調査の連絡があった際の事前準備から、調査当日の立会い、税務署との折衝までを一貫してサポートします。調査官からの専門的な質問に対し、経営者に代わって的確に主張・反論します。万が一、税務調査の連絡が来た際の具体的な準備や流れについては、こちらの記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
▶ 税務調査の連絡が来ても慌てない! プロが語る「社長がやるべき準備」と「税理士への頼み方」 - 融資サポート・事業計画書作成支援
銀行など金融機関からの融資を受ける際に必要となる事業計画書の作成を支援します。金融機関が納得する説得力のある資料作りをサポートし、時には金融機関の紹介や面談の同席も行います。 - 相続・事業承継、不動産売却などの臨時対応
経営者の相続が発生した場合の相続税申告や、後継者へ事業を引き継ぐ際の計画策定、会社や個人が所有する不動産を売却した際の譲渡所得税申告など、通常業務とは異なる専門的な対応を依頼する場合も別途費用となります。
料金表あり顧問税理士の費用・顧問料の相場を徹底解説
顧問税理士に依頼する上で最も気になるのが費用でしょう。顧問料は、会社の事業形態(法人か個人か)、売上規模、そしてどこまでの業務を依頼するか(記帳代行の有無など)によって大きく変動します。
以下に、一般的な費用相場をまとめました。あくまで目安としてご活用ください。
| 種別 | 事業規模(年間売上) | 税理士顧問料(月額)の相場 |
|---|---|---|
| 個人事業主 | 1,000万円未満 | 1万円~2.5万円 |
| 個人事業主 | 1,000万円以上 | 2万円~5万円 |
| 法人 | 1億円未満 | 3万円~5万円 |
| 法人 | 1億円~5億円 | 5万円~10万円 |
| 法人 | 5億円超 | 10万円~ |
※上記は記帳代行を自社で行う場合の相場です。記帳代行を依頼する場合、1万円~3万円程度上乗せされることが一般的です。
顧問料以外にかかる費用
注意すべきは、年間に支払う費用は月額顧問料の12ヶ月分だけではない、という点です。前述の通り、多くの税理士事務所では以下の費用が別途発生します。
- 決算申告料:月額顧問料の4~6ヶ月分
- 年末調整費用:基本料金+(従業員数 × 単価)
- 税務調査立会料:日当5万円~10万円程度
例えば、月額顧問料3万円の法人の場合、年間の支払総額は「3万円×12ヶ月+決算料18万円=54万円」程度が一つの目安となります。
顧問税理士を契約する5つのメリット費用以上の価値とは

毎月の顧問料を負担に感じるかもしれませんが、信頼できる顧問税理士は、その費用を上回る価値を会社にもたらしてくれます。主なメリットを5つご紹介します。
- メリット1:経営の意思決定が迅速かつ的確になる
資金調達、設備投資、人事採用など、経営上の重要な判断を行う際に、財務・税務の観点から専門的なアドバイスを即座に得られます。「主治医」がいる安心感は、経営者が大胆かつ的確な意思決定を下すための大きな支えとなります。 - メリット2:税務リスクを大幅に低減できる
日々の会計処理をプロの目でチェックしてもらうことで、申告漏れや計上ミスといった税務上のリスクを未然に防ぎます。万が一、税務調査が入った場合でも、会社の状況を熟知した専門家として、税務署に対して論理的な主張を行ってくれます。 - メリット3:適切な節税や資金調達のチャンスを逃さない
毎年のように改正される複雑な税制の中から、自社が活用できる控除や特例を適用し、合法的な節税を実現します。また、最新の補助金・助成金といった資金調達に関する情報提供を受けられることも大きなメリットです。 - メリット4:金融機関からの信用が高まる
税理士が作成・署名した決算書は、金融機関からの信頼性が格段に高まります。これにより、融資審査がスムーズに進んだり、より有利な条件での借り入れが可能になったりするケースがあります。 - メリット5:経理業務の負担が減り、本業に集中できる
記帳代行や給与計算を依頼すれば、経営者や社員が煩雑な経理業務から解放され、売上を創出するコア業務に集中できます。これは、特に人手が限られる中小企業にとって計り知れない価値があります。
顧問税理士は“いらない”?契約しない場合の3つのデメリット
「会計ソフトも進化しているし、顧問税理士は必要ないのでは?」と考える方もいるでしょう。確かに、売上がまだ少ない個人事業主の方など、ご自身で対応できるケースもあります。しかし、一定規模以上の事業者や法人が顧問税理士をつけない場合、以下のようなデメリットが生じる可能性があります。
- デメリット1:申告ミスや過少申告のリスクが増大する
税法は非常に複雑で、専門家でなければ正確な判断が難しいケースが多々あります。意図せずとも申告内容に誤りがあった場合、追徴課税や延滞税といったペナルティが課され、結果的に顧問料より高くついてしまう可能性があります。 - デメリット2:税務・会計業務に時間を取られ事業に集中できない
経営者自らが不慣れな会計処理や税務申告に時間を費やすことは、大きな機会損失です。その時間を営業や商品開発といった本業に充てていれば得られたであろう利益を考えると、コストパフォーマンスが良いとは言えません。 - デメリット3:有益な情報(節税・補助金など)を逃してしまう
税制の優遇措置や返済不要の補助金・助成金は、知っているか知らないかでキャッシュフローに大きな差を生みます。顧問税理士がいれば、自社に関連する有益な情報をタイムリーに入手できますが、いなければ自力で探し続ける必要があり、多くの情報を見逃すことになります。
失敗しない顧問税理士の選び方7つの重要ポイント

いざ顧問税理士を探そうと思っても、何を基準に選べば良いか迷ってしまいますよね。ミスマッチを防ぐために、必ず確認すべき7つのポイントをご紹介します。
- ポイント1:料金体系が明確でわかりやすいか
「どこまでが顧問料の範囲で、何が追加料金になるのか」を書面で明確に提示してくれる税理士を選びましょう。契約後に「これも別途費用です」といった話が出てくるようでは信頼関係を築けません。 - ポイント2:自社の業界に関する知識や経験があるか
飲食、建設、IT、不動産など、業界によって会計処理や税務上の慣行は異なります。自社の業界に精通した税理士であれば、より的確で実践的なアドバイスが期待できます。 - ポイント3:サポート体制は十分か
所長税理士一人だけの事務所か、複数のスタッフがいる税理士法人かによって、サポート体制は異なります。窓口となる担当者が誰で、いざという時に所長税理士が対応してくれるのか、といった点も確認しましょう。 - ポイント4:質問や相談へのレスポンスが速いか
経営判断にはスピードが求められます。質問に対して数日間返信がないような税理士では、ビジネスチャンスを逃しかねません。問い合わせ時の対応速度も重要な判断材料になります。 - ポイント5:クラウド会計などのITツールに強いか
今やクラウド会計ソフトの活用は業務効率化の必須条件です。ITに強く、新しいツールを積極的に活用している税理士を選ぶことで、自社のバックオフィス業務全体の改善につながります。 - ポイント6:人柄の相性が良く、長期的な関係を築けそうか
顧問税理士は、会社のデリケートな情報も共有する重要なパートナーです。話しやすいか、偉そうな態度を取らないか、会社の未来を一緒に考えてくれるか、といった人柄の部分は非常に重要です。 - ポイント7:必ず複数の税理士と面談して比較する
最初から一人に絞らず、少なくとも2~3人の税理士と面談し、提案内容や料金、相性を比較検討しましょう。「相見積もり」を取ることで、自社にとっての適正な条件が見えてきます。
これらのポイントに加えて、さらにプロの視点から「良い税理士」と「ダメな税理士」を具体的に見分ける方法については、こちらの記事もぜひ参考にしてください。
▶ 【プロの視点で斬る】良い税理士・ダメな税理士の見分け方 | 7つのポイント
【プロが推奨】顧問税理士の探し方6選!あなたに合う方法は?
では、具体的にどうやって顧問税理士を見つければ良いのでしょうか。ご自身の状況や考え方に合わせて、最適な方法を選びましょう。
- 当サイト「税理士コラボネット」で特徴を比較して探す
ご自身の目で直接、税理士の強みや特徴を比較検討したい方におすすめの方法です。当サイトでは、私たちが直接お会いしてお話を伺った税理士の先生方の特徴や強みを、インタビュー形式で詳しくご紹介しています。まずは「近くの税理士を探す」からお住まいの地域の先生方のプロフィールをご覧いただき、気になる事務所のホームページやGoogleマップの口コミなどを確認した上で、問い合わせてみると良いでしょう。 - 税理士紹介サイト(マッチングサービス)で紹介してもらう
「自分で探す時間がない」「第三者の視点で最適な税理士を紹介してほしい」という方には、専門の紹介サイトが便利です。希望条件を伝えるだけで、コーディネーターが間に入り、複数の税理士を紹介してくれます。代表的なサービスには「税理士紹介センタービスカス」や「税理士ドットコム」などがあります。どのサイトが良いか迷った際は、こちらの比較記事も参考にしてみてください。
▶ 税理士紹介サイトおすすめランキングTOP5!プロが徹底比較 - 知り合いの経営者から紹介してもらう
信頼できる経営者仲間からの紹介は、安心感が高い方法の一つです。しかし、友人にとって良い税理士が、必ずしも自社に合うとは限りません。また、万が一相性が悪かった場合に断りにくいという側面も考慮しておく必要があります。 - 日本税理士会連合会の「税理士情報検索サイト」で探す
全国の税理士が登録されている公的なデータベースです。地域や得意分野で検索でき、客観的な情報に基づいているため信頼性があります。ただし、各税理士の人柄や詳細な実績までは分からないため、あくまで候補者リストアップの一つの手段と考えると良いでしょう。
▶ 税理士情報検索サイト - 取引のある金融機関に紹介してもらう
普段から付き合いのある銀行や信用金庫に相談してみるのも有効です。金融機関は融資先の経営状態を把握しており、事業内容を理解した上で、融資に強い信頼できる税理士を紹介してくれる可能性があります。 - 税理士が回答しているQ&Aサイトで探す
一般の方からの税務に関する質問に、税理士が回答しているオンラインのQ&Aサイトも参考になります。回答内容から、その税理士の専門性や人柄、説明の分かりやすさなどを判断し、直接連絡を取ってみるという方法です。
【実践編】顧問税理士を「経営参謀」としてフル活用する5つのコツ

最後に、顧問契約の価値を最大限に引き出すための、経営者自身が実践すべき5つのコツをお伝えします。受け身の姿勢から一歩踏み出すだけで、関係性は劇的に変わります。
- コツ1:「月次試算表」をただ受け取るだけでなく、質問する
毎月送られてくる試算表を、ただ眺めてファイリングするだけでは宝の持ち腐れです。「先月より売上が落ちた原因は何だと思いますか?」「この経費率を改善するアイデアはありますか?」といった質問を投げかけてみましょう。数字のプロからの客観的な意見は、経営のヒントに繋がります。 - コツ2:「未来の話」を積極的に相談する
税理士との会話が、過去の業績報告だけで終わっていませんか?「来月、新しい設備投資を考えている」「半年後に、新しいスタッフを雇いたい」といった、これからの計画を積極的に話しましょう。「この計画の税務上のリスクは何ですか?」と聞けば、思わぬ落とし穴を事前に教えてくれるはずです。 - コツ3:定期面談を「自分から」設定し、議題を用意する
「先生、来週30分だけお時間ください。〇〇の件で相談したいです」というように、あなたから面談をセッティングしましょう。そして、その際には必ず「相談したいことリスト(アジェンダ)」を事前に共有しておくのです。これにより、税理士側も準備ができ、密度の濃い打ち合わせが可能になります。 - コツ4:税理士の「専門外」のことも、まずは相談してみる
「この悩みは、弁護士さんかな…」「補助金のことは、どこに聞けば…」そう思ったときも、まずは顧問税理士に話してみましょう。経験豊富な税理士は、弁護士、司法書士、社会保険労務士といった、他の専門家との幅広いネットワークを持っています。あなたに最適な専門家を紹介してくれる、優れた「ハブ」の役割を果たしてくれます。 - コツ5:会社の「良いニュース」も「悪いニュース」も共有する
大きな契約が取れた、という良いニュースは、将来の納税額に影響します。逆に、大口の取引先を失った、という悪いニュースは、資金繰りに直結します。会社の状況を包み隠さず共有することで、税理士はより早く、より的確な手を打つことができます。良いことも悪いことも話せる関係こそが、真のパートナーシップです。
「顧問税理士とは?業務内容から選び方まで」まとめ
- 顧問税理士とは
単なる申告代行者ではなく、会社の財務・税務を継続的にサポートし、共に成長を目指す「経営パートナー」である。 - 費用相場
法人は月額3万円~、個人事業主は月額1万円~が目安。ただし、決算料などが別途発生するため、年間の総額で考えることが重要。 - メリット・デメリット
適切な節税やリスク低減など多くのメリットがある一方、契約しない場合は機会損失や申告ミスのリスクを抱えることになる。 - 選び方・探し方
料金の明確性や業界知識、相性など複数の視点で比較検討することが不可欠。自社に合った探し方で、信頼できる候補を見つけることが成功の鍵。 - 活用のコツ
顧問契約の価値は経営者自身の活用姿勢で決まる。受け身にならず、未来の相談や積極的な質問を心がけることが「経営参謀」を育てる。
顧問税理士は、あなたの会社に最も近い外部の専門家です。その知見とネットワークを最大限に引き出すことで、月々の顧問料は、何倍もの価値となってあなたの会社に返ってくるはずです。ぜひ、この記事を参考に、貴社にとって最高の「経営参謀」を見つけてください。
「顧問税理士」に関するよくある質問
必ずしも必要ではありませんが、売上が1,000万円を超え、消費税の課税事業者になったタイミングは一つの検討時期です。また、利益(所得)が300万円~500万円を超えてくると、税務調査の可能性も高まるため、専門家をつけた方が安心です。節税や資金調達を積極的に行いたい場合も、売上規模にかかわらず顧問契約を検討する価値はあります。
一般的に、年に一度の「決算申告料」(月額顧問料の4~6ヶ月分)と、従業員がいる場合は「年末調整費用」が別途かかります。また、税務調査が入った際の「立会料」や、銀行融資のサポートを依頼した場合の成功報酬などが追加で発生することがあります。契約前に、追加費用の体系をしっかり確認しておくことが重要です。
格安の顧問料には、サービス内容が限定的であるなどの理由があります。例えば、「相談はチャットのみ」「面談は年1回」「記帳代行は含まない」といったケースです。単に申告書を作成するだけの役割を求めるなら問題ないかもしれませんが、経営相談や節税提案といった付加価値を期待するのは難しいでしょう。自社が何を求めるかを明確にした上で判断することが大切です。より詳しいメリット・デメリットは、こちらの記事も参考にしてみてください。
▶ 格安税理士のメリット・デメリット 「安かろう悪かろう」を避けるための注意点
まず、現在の契約内容を確認し、解約の申し出時期や方法を確認します。一般的には2~3ヶ月前までに伝えるのがマナーです。次に、新しい税理士を決め、過去数年分の申告書や総勘定元帳などのデータを引き継いでもらいます。円満に引き継ぎを行うためにも、感情的にならず、感謝を伝えた上で事務的に進めることが重要です。より詳しい手順や、トラブルなく引き継ぐための具体的な方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
▶ 税理士の変更、どう進める?トラブルなくスムーズに引き継ぐ手順とスマートな断り方
ほとんどの場合、記帳代行や給与計算は月額顧問料には含まれず、別途オプション料金となります。記帳代行は仕訳数、給与計算は従業員数に応じて料金が設定されているのが一般的です。顧問契約の基本サービスに含まれるのは、あくまで自社で作成した会計帳簿のチェックと、それに基づく税務相談や経営アドバイスです。
「税理士」は資格の名称です。一方、「顧問税理士」は、その税理士と継続的な「顧問契約」を結んでいる場合の呼び方です。確定申告だけを単発で依頼した場合は「税理士」ですが、毎月定額の報酬を支払い、継続的に経営や税務の相談に乗ってもらう契約を結ぶと、その税理士が自社の「顧問税理士」となります。
はい、事業に関する相談や業務の対価ですので、全額経費として計上できます。一般的に、月々の顧問料は「支払手数料」や「支払報酬料」、または「業務委託費」といった勘定科目で処理します。決算料なども同様の科目で問題ありません。
以下の4点は必ず確認してください。
1. 業務の範囲(どこまでが顧問料に含まれるか)
2. 報酬額(月額顧問料、決算料、その他の追加料金)
3. 契約期間と解約条件(解約の申し出時期や方法)
4. 守秘義務に関する条項。
これらの内容に不明な点があれば、署名する前に必ず質問しましょう。
顧問税理士がいるからといって、税務調査の確率がゼロになるわけではありません。しかし、税理士が毎月の会計をチェックし、適正な申告を行っているため、申告内容の信頼性が高まり、結果として調査対象に選ばれにくくなる傾向はあると言われています。また、税理士法33条の2の書面添付制度を利用している場合、調査が省略される可能性もあります。
はい、可能です。近年はクラウド会計ソフトとWeb会議システムの普及により、全国対応の税理士事務所が増えています。物理的な距離に関係なく、自社の業界に強い、相性の良い税理士を選ぶことができます。ただし、税務調査の際には現地に来てもらう必要があるため、その際の交通費などの取り扱いについては事前に確認しておくと良いでしょう。